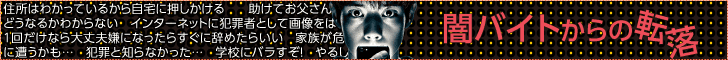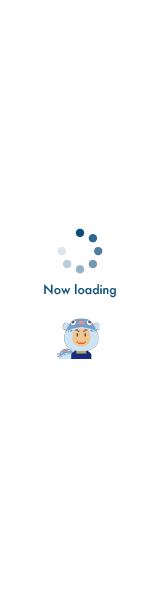◾️サッカー部出身のサッカー選手
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
森直樹 1972 1990 長崎県 DF 名古屋グランパスエイト 現役引退
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
立花由貴 1979 1997 熊本県 DF 明治大学 横河武蔵野FC 現役引退。横河武蔵野FC コーチ
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
近藤健一 1983 2001 長崎県 GK FC東京 現役引退
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
田中政勝 1987 2005 熊本県 DF 明治大学 V・ファーレン長崎 マンリー・ユナイテッドFC
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
名前 生年度 卒年度 経歴
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
小嶺 忠敏(こみね ただとし、1945年6月24日 - 2022年1月7日)は、日本の元高校教員、サッカー選手、サッカー指導者(JFA 公認S級コーチ)。一般社団法人長崎県サッカー協会会長、長崎総合科学大学特任教授。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
サッカー部を持つ企業へ大卒後の就職が内定していたが、母校の長崎県立島原商業高校時代のコーチから誘いを受けて教員を目指し、長崎県の教員採用試験に合格して地方公務員となった。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
定年退職後は一般社団法人長崎県サッカー協会の会長(2004年6月10日就任)、長崎県教育委員会参与、特定非営利活動法人「V・ファーレン長崎スポーツコミュニティ」理事長(2006年5月27日付で副理事長から昇格)なども務めている(後の参院選立候補に伴い、一部役職は辞任した)。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
2017年3月、前月より続いているV・ファーレン長崎の経営問題の収拾を図る目的で、同チームのアカデミー部門を担当する「一般社団法人V.V.NAGASAKIスポーツクラブ」の代表理事に就任した。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
◆国見高時代◆
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
株式会社日立製作所(ひたちせいさくしょ、英: Hitachi, Ltd.)は、日本の電機メーカーであり、世界有数の総合電機メーカー。日立グループの中核企業であり、春光グループの春光会、芙蓉グループの芙蓉懇談会、旧三和銀行の取引先企業で構成されるみどり会の会員企業でもある。日経平均株価およびTOPIX Core30、JPX日経インデックス400の構成銘柄の一つ。通称は日立やHITACHI、日製(にっせい)など。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
◾️営業利益
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
全世界に製造・販売拠点を広げる多国籍企業でもあり、売上の59%は日本国外からもたらされる(2021年現在)。米国誌『フォーブス』が毎年発表する世界企業ベスト2000では、コングロマリット(複合企業体)に分類されていたが、近年はコングロマリットディスカウントに対応するため、事業の選択と集中を徹底して子会社を削減する傾向にあり、2019年にはエレクトロニクスに分類された。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
2009年4月、業績悪化の責任をとり、取締役会長の庄山悦彦と代表執行役執行役社長の古川一夫が退任し、元副社長で日立マクセル(現・マクセル)、日立プラントテクノロジーの取締役会長、元日立ソフトウェアエンジニアリング代表執行役の川村隆が代表執行役執行役会長兼執行役社長に就任。同時に、グループ会社に転出していた元副社長3名も副社長に復帰し、経営改革が進められた。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
◾️出資該当会社
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
十代 中西宏明 2010年 - 2014年 東京大学工学部
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
1937年:国産工業(現在:日立金属の前身企業)と合併。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
1995年
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
2007年
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
2011年
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
2016年
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
2018年
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
2021年
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
◾️スポーツ事業
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
◾️かつて存在したチーム
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
・日立栃木サッカー部(サッカー・JFL):撤退、クラブチーム化
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
船橋市立船橋高等学校(ふなばししりつ ふなばしこうとうがっこう)は、千葉県船橋市市場四丁目にある市立高等学校。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
◾️著名な出身者: サッカー
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
茶野隆行 千葉県市川市 1976 1994 DF ジェフ市原(日本代表) 現役引退
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
羽田憲司 千葉県市川市 1981 1999 DF 鹿島アントラーズ 現役引退。松本山雅FCコーチ
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
原一樹 千葉県松戸市 1984 2002 FW 駒澤大学 清水エスパルス 現役引退
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
若狭友佑 千葉県松戸市 1989 2007 MF 青山学院大学 東京武蔵野シティFC 現役引退
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
井岡海都 千葉県 1998 2016 GK 仙台大学 ベガルタ仙台 ベガルタ仙台
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
全国高等学校サッカー選手権大会(ぜんこくこうとうがっこうサッカーせんしゅけんたいかい、英語: All Japan High School Soccer Tournament、全国高校サッカー選手権大会)は、高校男子サッカー部の頂点を決めるサッカーの大会。各都道府県代表48校(東京都は2校)による、トーナメント戦で行われる。通称「選手権」「冬の国立」「冬の高校サッカー」。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
◾️歴史
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
◾️創設の経緯
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
こうした他地域からの参入があれば、試合結果が変わるのは勿論、「高校サッカー選手権」の前身である「中学校蹴球大会」とは認められなかったかも知れない。後述するが、同時期に各地で「全国中等学校蹴球大会」と名乗る大会が数多く開催されたが、どれも参加は師範学校と旧制中学校のみで、これ以上のカテゴリーのチームの参加はなく、またこれらの大会には他地域からの参加があった(#記録上の問題点)。大会は大阪朝日新聞社主催の全国中等学校優勝野球大会に対抗するべく、ラグビー競技の大会をメインとして始めたため、サッカー関係者には相談がなかった。『日本サッカーのあゆみ』には「蹴球関係者側の意見を尊重してもらう余地もなく、新聞社の方が先に立った」と書かれている。この毎日新聞が主催して大阪で始まった大会を現在の高校選手権の前身としている。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
◾️他地域の大会
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
大日本蹴球協會はこの大会の3年後の1921年に設立されるが、設立にあたり中心的に動いたのが内野台嶺ら東京高等師範の関係者で「關東蹴球大會」を主催した東京蹴球団を設立したのも内野、後援した朝日新聞社側の担当者が東京府青山師範学校OBで東京蹴球団の選手でもあった山田午郎、「關東中等学校蹴球大會」の名誉会長を務めた嘉納治五郎は、大日本体育協会会長でもあり当時、東京高師の校長でもあった。大日本蹴球協会も初期の間は、師範学校系の幹部たちが力を持っていたため、彼らの多くが関与した「關東中等学校蹴球大會」の方をある時期までは支持していたためと見られる。毎日新聞主催の大会は、当初は大日本蹴球協会がタッチできなかったと言われるが第9回大会からの全国大会移行にあたっては野津謙ら、大日本蹴球協会の大学OBが関与したため彼ら大学OBが大日本蹴球協会内で力を増すに連れ「毎日新聞社主催大会」が支持を増やしていったのかも知れない[独自研究?]→#全国大会へ(第9回〜)。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
翌1919年には神戸高商主催(朝日新聞社後援)で、毎日新聞主催の大会とほぼ同じ出場チームによる「全国中等学校蹴球大会」が、1921年から名古屋蹴球団主催、新愛知新聞社(現:中日新聞社)後援による「全国中等学校蹴球大会」が、1924年には岐阜蹴球団主催の「全国中等学校蹴球大会」、八高主催の「全国中等学校蹴球大会」、東京高等師範学校主催の「全国中等学校蹴球大会」が、1925年には関西学院高等部主催(大阪毎日新聞社後援)の「全国中等学校ア式蹴球大会」が、その他刈谷中学や広島高専主催でも「全国中等学校蹴球大会」と名乗る大会が、その後全国各地で新聞社や蹴球団、大学、旧制高校、師範学校など、学校主催による「中等学校蹴球大会」がいくつも行われるようになり、競技会の乱立時代といわれた。1932年から1933年にかけては、全国各地で22も中等学校のサッカー大会があった。1933年に関西大学主催で行われた「関西中等学校蹴球大会」などは、他地域からの参加も含めて37校が集まる大きな大会で同年の毎日新聞主催大会の参加12校を大きく上回る規模であった。八高主催の「全国中等学校蹴球大会」第1回大会(1924年)には、関西や広島からも参加があったように「全国中等学校蹴球大会」と付けられた大会や、先の「關東中等学校蹴球大會」「東海蹴球大會」などは、所在地域の参加が主で全国規模の参加まではいかないが、どの大会にも他地域からの参加があった。ところが、毎日新聞社主催の大会は「日本フートボール優勝大會」と名乗っていても、第1回から1925年の第8回大会までの間、関西以外の学校は一校も参加がなかった。「全国中等学校蹴球大会」という名前の大会が多いのは、主導権争いが目的であったといわれる。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
1934年に大阪の毎日新聞社主催の大会に一本化されたが(#大会の一本化)、現在の高校選手権は、これら全てを源流とする見方も出てきている。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
サッカーの「関東中等学校蹴球大会」は、この大会名で朝日新聞に広告も打った。大新聞に「中等学校大会」と広告も打って普通に師範学校が出場しているのだから、特に問題はなかったものと思われる。本来は師範学校と中学の部は分けて行うべきなのだが、しかしこの二分野を別立てすると大会そのものが成立しなかったと『東蹴六十年史草稿』22頁に書かれている。それが何故なのかはこの本に書かれていないが、この時代サッカーをやっている学校自体が少ないから、師範学校と中学を別々に分けるとチーム数が少なくなり、例えば各5チームずつの参加ではトーナメント大会として成立し難く盛り上がりに欠ける、あるいは、元々サッカー自体に人気がない上、中学の大会ならまだしも、師範学校の大会は地味で人気がなく、師範学校だけの大会では成り立たなかったため一緒にやらざるを得なかった、等といった理由が考えられる。毎日新聞社主催の「日本フートボール優勝大會」は、カテゴリーを問いていないので、この問題は本来関係がないが、その毎日新聞社主催大会を第9回大会から全国大会に移行させるおり、この二つを分けるという案を大日本蹴球協会が出したが、毎日新聞社側に断られたという。新聞社がスポーツの大会を支援するのは、新聞の拡販や、広告獲得などの目的があるためと見られ、新聞社の主催でない学校主催の大会では、この二つを分けて開催することがあった。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
東京高等師範学校主催の「全国中等学校蹴球大会」では1924年の第1回大会から、師範学校の部と中学の部は別々に行われた。八高主催の「全国中等学校蹴球大会」でも、1926年の第4回大会からこの二つを分けている。この他、旧制大学、旧制高等学校、大学予科、大学専門部、高等師範学校、旧制専門学校は、師範学校とは年齢が重なる場合もあるが、旧制中学とは年齢が上で重ならないため、これらに所属するチームが「中学校大会」に参加することはあっても、優勝を争うトーナメントのような公式試合で対戦することはない。中学校と対戦することがあるのは模範試合や練習試合である。前述したように毎日新聞主催の大会に関西学院高等部や神戸高商が出場したのは「中学校大会」ではないからで、このように「中学校大会」と銘打っていない年齢制限などを設けていない大会では対戦することがあった。広島一中や神戸一中などは、中学校でも強かったから、天皇杯の本戦や極東選手権の日本代表全国予選などに出場し、これら上のカテゴリーのチームとも対戦した。なお、旧制高等学校は1923年から「全国高等学校ア式蹴球大会」が、旧制大学、大学予科、旧制専門学校なども各地で大会やリーグ戦があった。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
◾️毎日新聞主催(第1回 - 第8回大会)
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
また当時の交通事情は非常に悪く、賀川浩は「当時の遠征試合はハンディキャップが物凄く大きいため、地元の大会で御影師範や神戸一中が勝ってもあまり威張れない」などと述べている。1921年に名古屋蹴球団主催、新愛知新聞社(現:中日新聞社)後援による「全国中等学校蹴球大会」が、東京府青山師範学校、豊島師範、明倫中学、愛知一師、御影師範、姫路師範など、関東、東海、関西地区から10チームが参加して名古屋で行われたが、ここでも御影師範は関東の東京府青山師範学校に敗れている。この大会の決勝戦は東京府青山師範学校×明倫中学である。御影師範は毎日新聞主催の第1回大会から第7回大会までを七連覇するが、他の大会に出場すると負けることがあったことから、この毎日新聞の大会は、他の多くの大会と同程度のレベルであったと考えられる。大会の権威に関していえば、『高校サッカー60年史』の32頁に「東京ではそうでもなかったらしいが、大阪では大新聞の主催でないと大会に権威がなかった」、38頁に「私達御影師範では毎日新聞の大会を最高峰としていて、他の蹴球大会は前哨戦、準備大会位に考えていた」という記述や、『兵庫サッカーの歩み-兵庫県サッカー協会70年史』107頁に「大日本蹴球協会が設立される(1921年)まで、最も権威のあるフットボール大会は大毎の主催する全国蹴球大会で、その後も関西では蹴球大会の最高峰の一つであった」という記述が見られるから、関西の他の大会よりは権威があったのかも知れない。しかし、神戸一中の選手たちは「近畿のチームだけの毎日新聞の大会より、広島一中や広島高師附属中学の広島勢が来る神戸高商主催の大会で勝つ方が値打ちがある」と言っていたという賀川浩の証言もある。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
静岡県立藤枝東高校のサッカー部60年史には、「われわれ志太中学(藤枝東高校)の全国大会の初優勝は、1931年の東京高等師範学校主催の「全国中等学校蹴球大会」で、此処に全国津々浦々に志太中サッカーの名声を響かせた」と書かれている。この東京高等師範学校主催の「全国中等学校蹴球大会」というのも、1924年から1932年に9回開催された全国規模の中等学校サッカー大会で、東日本の学校がほとんどだが、近畿や東海地区の学校も参加した大きな大会であった。志太中学は毎日新聞主催の大会が全国大会になっても、戦前には毎日新聞主催の大会の予選には出場していないようで、つまり学校によっては、特に関西以外の学校にとっては、毎日新聞主催の大会を唯一の全国大会とは捉えておらず、乱立していた他の全国大会等を選んで出場していたものと見られる。毎日新聞社主催の大会が1925年度の第9回大会から全国大会となり"名実とともに全国大会として発展した"と書かれた文献もあるが、すぐに唯一の全国大会と認知された訳ではなく、徐々に認知されていって、"名実とともに全国大会""唯一の全国大会"として完全に認知されたのは、1934年に毎日新聞社主催の大会に一本化され、他の全ての大会が終了した第16回大会以降の話と考えられる。これらの事情を考えれば「全国高等学校サッカー選手権」が"真の全国大会"と文句なくいえるのは、1934年の第16回大会からでないかと思われる。『高校サッカー40年史、60年史』の「全国高等学校サッカー選手権大会」の記述は、関西の関係者の証言がほとんどで、他の地域の大会はほとんど触れられていない。[独自研究?]
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
『高校サッカー60年史』32頁に「毎日新聞主催の大会は準備委員会がともかく強力で、大日本蹴球協会ができてからも、協会はタッチできなかった」、また「關東蹴球大會」を主催した東京蹴球団の団史には「東京ではサッカーの関係者が主体で、朝日新聞の方が善意の後援をしてくれたのだが、他の二つは新聞社の方が強力に推進された。これはこれらの地域のサッカー関係者が、まだ微力だったといった方がよいのかも知れない」と書かれており、サッカー関係者としては、この毎日新聞主催の大会は、当初は大阪の新聞社が勝手にやっているという考えであったのかも知れない。やはりこの毎日新聞の大会が後に高校選手権の前身ということになったから重みを増したことは間違いがない。前身ということにならなかったら、他の多くの大会と同様の位置づけであったと考えられる。[独自研究?]第8回大会は、旧制専門学校と中学の部を分けて実施した。専門学校の部の出場チームは早稲田高等学院、官立神戸高商、松山高等学校、関西大学、関西学院の5校で、決勝は早高2-1関学。何故分けて実施したのかは『高校サッカー60年史』にも記述がないが、翌年の「全国中等学校蹴球選手権大会」移行に伴い、カテゴリーが明らかに中学より上のチームを切り離すということかも知れない。各試合の結果他、詳細が『高校サッカー60年史』に書かれておらず、翌年の第9回大会以降の大会に旧制専門学校の部の結果は記載がない。『輝く埼玉サッカー75年の歩み』1082頁には「第8回大会"から"高専の部と中等学校の部に分け、会場も甲子園球場に移って開かれたのである」と書かれているため、その後も継続されたと見られるが詳細は不明。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
◾️全国大会へ(第9回〜)
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
◾️大会の一本化
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
 ポスト
ポスト