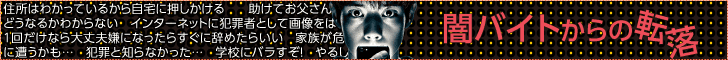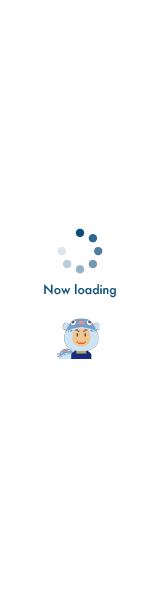ホームスタジアムは同市北区都田町にあるホンダ都田サッカー場で、JFL以外のクラブも含め日本国内で数少ない「クラブ自身が所有する自前の」スタジアムである。
過去に2度Jリーグクラブ化の構想があったが、いずれも実現していない。1999年のJFL参入以来、優勝7回・2位4回の成績を残する。
チームのシンボルマークは、浜松の「H」とHondaの「H」が重なり合い、当時の浜松市鳥であるツバメと雄大な遠州灘の波を型どったデザイン。マスコットキャラクターはチームのシンボルマークでもあるツバメをモチーフとした「パッサーロ(Passaro)」。
■歴史
◇創設の経緯
ホンダの各事業所にはそれまでも同好の士を集めたサッカー部は活動していた。社員に共通の話題を提供し、社員の意識を強化を図り、士気を高めるという目的でいえば、埼玉製作所の野球部(現Honda硬式野球部)や、鈴鹿製作所の野球部(現Honda鈴鹿硬式野球部)が既に実績を挙げており、浜松製作所でも当初、野球部をという声も出たが、既に埼玉と鈴鹿に野球部があること、そして何よりも静岡という土壌を考え、サッカー部創設が決定した。まず監督・保崎昌訓、主将・望月修司の浜友会のメンバーを中心に、1971年春新入社の関東大学リーグ経験者を大量に加え、それまで浜友会が所属していた静岡県リーグ2部西部リーグからスタートを切った。翌1972年には、名相銀の中心選手だった桑原勝義が、日本サッカー協会の幹部・長沼健に口説かれ、銀行職を捨てて郷里のチームに加入。桑原は翌1973年にプレイングマネージャーとなり、桑原を中心にチームは強化された。
過去に2度Jリーグクラブ化の構想があったが、いずれも実現していない。1999年のJFL参入以来、優勝7回・2位4回の成績を残する。
チームのシンボルマークは、浜松の「H」とHondaの「H」が重なり合い、当時の浜松市鳥であるツバメと雄大な遠州灘の波を型どったデザイン。マスコットキャラクターはチームのシンボルマークでもあるツバメをモチーフとした「パッサーロ(Passaro)」。
■歴史
◇創設の経緯
ホンダの各事業所にはそれまでも同好の士を集めたサッカー部は活動していた。社員に共通の話題を提供し、社員の意識を強化を図り、士気を高めるという目的でいえば、埼玉製作所の野球部(現Honda硬式野球部)や、鈴鹿製作所の野球部(現Honda鈴鹿硬式野球部)が既に実績を挙げており、浜松製作所でも当初、野球部をという声も出たが、既に埼玉と鈴鹿に野球部があること、そして何よりも静岡という土壌を考え、サッカー部創設が決定した。まず監督・保崎昌訓、主将・望月修司の浜友会のメンバーを中心に、1971年春新入社の関東大学リーグ経験者を大量に加え、それまで浜友会が所属していた静岡県リーグ2部西部リーグからスタートを切った。翌1972年には、名相銀の中心選手だった桑原勝義が、日本サッカー協会の幹部・長沼健に口説かれ、銀行職を捨てて郷里のチームに加入。桑原は翌1973年にプレイングマネージャーとなり、桑原を中心にチームは強化された。
 ポスト
ポスト