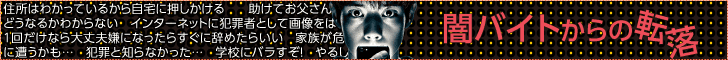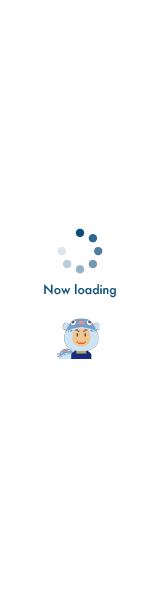全日空横浜サッカークラブは、かつて存在した日本のサッカークラブ。全日本空輸の子会社である全日空スポーツが運営をしていた。呼称は全日空。かつて日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)に加盟していた横浜フリューゲルスの前身となったクラブである。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
その後、名古屋相互銀行や永大産業で選手、指導者経験のある塩澤敏彦を監督に迎えると、1988年に1部復帰を果たし全日空サッカークラブに改称。前田治やフェルナンド・ダニエル・モネールらを擁して1988-89シーズンのJSL1部では2位、翌1989-90シーズンでは3位。天皇杯では1988年と1989年に2年連続でベスト4進出を果たした。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■ボイコット事件
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■歴代監督
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
住友金属工業蹴球団は、かつて存在した日本のサッカークラブ。住友金属工業(現・日本製鉄)のサッカー部として1947年に創部され、始めは大阪府、1975年からは茨城県鹿島郡鹿島町(現在の鹿嶋市)を拠点として活動していた。略称は住金。日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)に加盟する鹿島アントラーズの前身となったクラブである。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
1975年に大阪本社から稼動したばかりの鹿島製鉄所がある茨城県鹿島町(現在の鹿嶋市)に移転した。これ以降に本格的な強化が始まり、1985年にJSL1部に昇格した。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
1991年に元ブラジル代表のジーコを獲得。また地元自治体の支援を受け国内初となる全席オールシートのサッカー専用スタジアム(茨城県立カシマサッカースタジアム)の建設を発表するとこれが決定的な要因となり、初年度からのJリーグ参加が決定した。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■住友金属工業蹴球団に在籍した主な選手
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■関係する人物
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
【あの日、その時、この場所で】川淵三郎/前編 Jリーグは2DKの一室から始まった
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
1989年6月、日本サッカー協会はプロ化を目指して「プロリーグ準備検討委員会」を設置。13回もの同検討委員会を経て、91年2月には「オリジナル10」と呼ばれるリーグ最初の10クラブが決定し、3月「プロリーグ設立準備室」が立ちあがった。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
4人の事務局員に担当はなかった。オールラウンダーといえば聞こえはいいが、実際には役割分担をする余裕もなかったからだ。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
日本では使われていなかった「チェアマン」(理事長)の名称はよく知られる。他にもプロ野球で使われていた「フランチャイズ」。興行権の意味合いが強く、サッカーで使うには違和感がある。様々な表現を考え、一度は「本拠地」としたが、どこか馴染めず新しさもない。事務局、関係者が議論した結果、最後は「ホームタウン」となった。ホームタウンにはまさに新しい響きが備わり、その後、スポーツが企業を離れ、地域がスポーツを盛り上げるといった日本社会の構造的な転換にも影響力を発揮した。91年11月に発表されたリーグ名も、新しいものだった。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
当時54歳、古河電工から古河産業に出向しており、仕事を抱えながら週4回は事務所に足を運んだ。古河産業の日本橋オフィスから事務所に行き、時には、事務所がひと段落するともう一度会社に戻って業務をこなし千葉へ帰宅する日もあった。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
1991年にJリーグへ加盟。ホームタウンは静岡県静岡市(合併前は清水市)。ホームスタジアムはIAIスタジアム日本平、練習場はエスパルス三保グラウンド。チーム名の「エス(S)」は「サッカー、清水、静岡」の頭文字で、「パルス(PULSE)」は英語で心臓の鼓動を意味する。1993年のJリーグ開幕を戦った10クラブ(オリジナル10)の一つで、10クラブの中では唯一母体となるクラブが実業団ではなく、かつ日本サッカーリーグ (JSL) に加盟していないクラブである。発足時の運営会社は株式会社エスラップ・コミュニケーションズ、1998年2月1日以降は株式会社エスパルス。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■クラブ発足の経緯
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■1991年〜1992年(静岡県リーグ)
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■エスパルス栄誉賞
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
◇新スタジアム構想
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
周辺の病院や高層マンションなどの騒音対策や、防災機能を兼ね備えた公園整備などの選択肢も考えられていること、更に東静岡駅の南側に静岡県草薙総合運動場陸上競技場、同球技場もあることからなお難航が懸念されており、実際、田辺市長は2014年9月の静岡市第3次総合計画の骨子案を発表した時もこの8年間で予定している計画案に何を建設するかを盛り込まず、事実上結論を出すことを凍結した影響から静岡県の川勝平太知事もサッカー場を建設すべきであるとする私見を述べている。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■関連施設
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
□■【FOOTBALL CHANNEL】■□
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
日本は前半30分、41分と失点。43分、木村のFKが決まって1点差に詰めるが、反撃及ばず1-2のまま終了のホイッスルを聞いた。11月3日の第2戦、敵地に乗り込んだ日本は0-1で敗れた。こうして、森監督率いる日本のW杯初出場の夢は散った。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
「ユース代表に選ばれてから、もっと上を目指したいと思うようになった。周りのレベルが上がって、サッカーがもっと面白くなって、それならA代表に選ばれればさらに楽しくやれるじゃろうと。そんなもんよ。たくさんの人に自分のプレーを見てほしい、知ってもらいたいという気持ちもあったね。だから、韓国戦で国立が満員になった時は、涙が出るほどうれしかった」
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■ プロ発足が早かった韓国。レベルの差を痛感
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■ どれだけ多くの人に夢や希望を与えられるかを知れば選手のプレーは変わる
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
「自分がたくさんの人に支えられ、どれだけ多くの人に夢や希望を与えられるか。それを知ることによってプレーが変わるんです。本物のプロとして、責任感のある重いプレーができるようになる。若い頃は分からないんだな、これが。俺もそうだったもの。早めに気づいた方がいいよと言えるくらいかな」
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
かつて日本代表チームの練習場といえば、千葉県の検見川グラウンドが定番だった。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
森は準備を整え、選手たちに伝えた。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
□■【SAMURAI BLUE】■□
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
ドーハの悲劇(Agony of Doha)は、1993年10月28日にカタールの首都・ドーハのアルアリ・スタジアムで行われたサッカーの国際試合、日本代表対イラク代表戦の日本における通称。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■最終予選の経過
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
第4戦終了時点で首位の日本は勝てば他会場の試合結果にかかわらず出場決定となり、日本が引き分けてかつサウジアラビアと韓国がどちらも勝った場合であっても、韓国が北朝鮮に1点差で勝利した場合には(即ち得失点差で日本と同数となる場合)、日本の総得点が韓国と同数以上であれば日本が出場権を得られるという、かなり有利な条件で日本は最終戦に臨んだ。一方、イラクは日本戦での勝利がまず必要となり、加えてサウジアラビア−イラン戦が引き分けかイランの2点差以内勝利(3点差以上の場合は得失点・総得点でイランとの争い)または韓国が北朝鮮に対し引き分けか敗れた場合、1986年メキシコ大会に続く2度目のW杯本大会出場が実現する状況だった。3位の韓国も自力出場の可能性が消滅しており、最終戦で勝利しても日本とサウジアラビアが共に勝利した場合は本大会出場ができない状況にあった。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■第5戦(最終戦)
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
◇後半戦
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
イラクの同点ゴールが決まった瞬間、控えを含めた日本代表選手の多くが愕然としてその場に倒れ込んだ。その後、日本はキックオフからすぐ前線へロングパスを出すも、ボールがそのままタッチラインを割ったところで主審のセルジュ・ムーメンターラーの笛が鳴らされ、2-2の引き分けで試合終了となった。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■放送
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
NHK BS1の放送では実況を山本浩アナウンサー、解説を田中孝司が務めた。スタジオでは友田幸岐が司会を務め、解説は岡田武史と田嶋幸三が担当した。試合終了後、岡田は言葉を詰まらせ、友田は「サッカーの怖さが出ました。何もこの試合じゃなくても良かったんじゃないかと…」とコメントした。岡田はこの4年後、1998年フランスワールドカップ最終予選中に急遽日本代表監督を引き継ぎ、ワールドカップ初出場を決めることになる(ジョホールバルの歓喜)。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■エピソード
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
川淵は日本への帰国便に乗る前、「明日から我々に厳しい批判の声が飛んでくるけれど、それを受け止めて、前へと進んでいこう」と声をかけた。しかし、選手達を乗せたチャーター便が成田国際空港に到着すると、数百人のファンから温かく出迎えられた。多くのマスコミやファンは、ワールドカップ出場を直前で逃したにもかかわらず、この結果を好意的に受け止めた。しかし、こういった反応はワールドカップ出場をギリギリで逃した選手たちにとって複雑なものだったという。松永は、「日本はサッカー先進国に向かっている途中だからこうなんだ。これがドイツやブラジル、スペインだったらこういう歓迎のされ方はしないんだろうな。これから代表を背負って戦っていく選手たちに対して、ここでブーイングされるときこそが本当の日本のサッカーのスタートなんだな」と感じたという。また実際に現場で取材したベテラン記者の中には、こうした国内の反応を苦々しく思う者もいたらしい。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
韓国の選手は本戦出場決定に大喜びし、試合後にホテルで祝勝パーティーを行った。しかし、部屋に戻りテレビで日本の選手・サポーターが泣く映像を見ると、誰もが声を失ったという。なお、日本と韓国はドーハの同じホテルに泊まっており、サンフレッチェ広島に所属していた盧廷潤の好意で焼肉とキムチをお裾分けしてもらったこともあった。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■分析
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
特に左サイドバック (SB) の都並敏史が左足を亀裂骨折した影響は大きく、左サイドで三浦知・ラモス・都並のヴェルディトリオが絡みながら、都並の攻撃参加を引き出すという武器が失われた。オフト監督と清雲コーチは70試合のスカウティングを重ねたが、都並の代役になりうる攻守のバランスがとれたバックアップは見つからなかった。悩んだオフト監督は「街で『あなたサッカーやってませんか?左サイドバック、できませんか?』と聞いて回りたいくらいだ」と清雲コーチに真顔で話したという。スペイン合宿でのレアル・ベティスとの練習試合では江尻篤彦をテストするも満足できず、最終予選の壮行試合を兼ねたアジア・アフリカ選手権(10月4日)ではボランチの三浦泰年を左SBに起用し[注 2]、一応の目途がついたと思われたが、最終予選第2戦でイランに三浦泰のいる左サイドを執拗に狙われ、第3戦以降はセンターバック(もしくは右SB)が本職の勝矢を左SBにコンバートした。勝矢は北朝鮮のキーマンであるキム・グァンミンを完封するなど守備面で貢献したが、攻撃面とのバランスは解決しなかった。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
イラク戦の後半、日本は中盤の運動量が落ちてボールを回収できず、ディフェンスラインが下がりっぱなしになりイラクの波状攻撃を浴びる状態だった。ピッチ上の選手は中盤のカンフル剤となる北澤豪の投入を望んでおり、ラモスはベンチに向かって「キタザワー」とリクエストしていた。しかし、オフト監督は韓国戦と同じく「長谷川→福田正博」「中山→武田修宏」という前線2人の交代を行い、結果的に劣勢を挽回する事が出来なかった。清雲コーチは「中盤の選手を入れると、イラクのディフェンダーが上がってきてプレッシャーがきつくなる。それが嫌だったんです」と交代策の意図を説明する。結果論にすぎないが、北澤は後に「やはり(あの交代は)間違いだったと思う」と述べている。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
◇チームの内情
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
イラク戦のハーフタイム中、ロッカールームに引き上げてきた選手たちは、オフト監督が3度も「Shut Up(黙れ)!」と怒鳴らなければならない程の興奮状態にあり、オフト監督の戦術説明を聞かず勝手に修正点を話し合っていた。清雲コーチによれば「選手たちの会話がどこで起こっているのかわからない異様な状況」で、「そんな混乱が続く中でオフトが『U.S.A. 45min』とホワイトボード上の模造紙に書いて説明しようとしたら、後半のブザーが鳴ってしまった」という。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
◇イラクの健闘
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
ロスタイムに入り主審がいつ試合終了の笛を吹くか分からない状況では、コーナーキックを直接ゴール前へ蹴るのが常識だった。イラクの選手がコーナーにボールをセットする間、柱谷はゴール前の人数と配置を確認して、これなら大丈夫と思ったという。しかし、日本選手の予想を裏切り、イラクのフセインはショートコーナーを選択した。松永は「もしゴールが逆だったら、イラクは電光掲示板を見ていたはず。そうしたら、イラクはショートコーナーなんて絶対やらなかったと思う。あいつらはロスタイムだってことを知らなかったんだ」と述べている。同年12月22日放送のNHKクローズアップ現代「空白の17秒 〜日本がW杯にもっとも近づいた日〜」でフセインはインタビュー答え、「試合に夢中で、時計を見る余裕がなかったので、時間が残っているのかいないのか分かりませんでした」と語った。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
イラク代表は最終予選を通じて全チーム中1位の得点数を叩き出していた。また日本戦までの星どりは1勝2分け1敗だったが、ワールドカップ本戦出場国の韓国・サウジアラビアを苦しめた上での2分け、唯一の黒星となった北朝鮮戦も後半途中退場者を出すまで2-0でリードしており、日本戦においても主力を多く欠く中での引き分けであった。ラモスも最終予選を振り返った時に強かったチームはとインタビューで聞かれると「間違いなく韓国とイラク。イラクは特にサッカーをよく知っているなと思った」と述懐している。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
 ポスト
ポスト