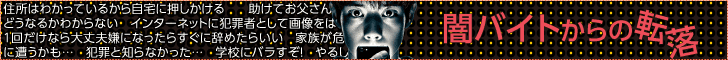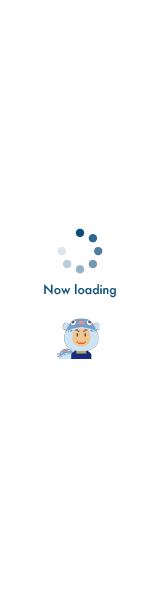□■【SAMURAI BLUE】■□
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■夢先生の紹介 | JFAこころのプロジェクト | 社会貢献活動
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
新型コロナの影響は、デッツォーラにとって、吉と出るか凶とでるか、、、
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
現時点での浜田市完全移転、再出発への評価は厳しい。2010年シーズンからの劇的復調からもう10年。県内全域ホーム構想は何処へ。。。わずかな可能性が残るとすれば、出雲市?あるいは、セントラル中国に原点回帰であれば少なからずチャンスが残るか。。。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
嵐も落ち着いたみたいで、ここからの、再出発を期待したい!!!
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
中国リーグは、トーナメント方式との書込みがちらほら。降格はなしか?!
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
マツダSCは、広島県を拠点とする、自動車メーカーマツダのサッカー部である。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■タイトル
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
攻めるなら出雲か!?デッツォーラの由来としては、出雲がしっくりくる!!!
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
古河電気工業株式会社(英文社名 Furukawa Electric Co., Ltd.)は、古河グループの光ファイバー・電線・ワイヤーハーネス等の製造を行なう非鉄金属メーカーである。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■主力製品・事業
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■主要取引先
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
公式がなかなか動かないけど、活動はFacebookメイン?
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
コピペがなくなってきたのは、前向きにとらえられる!
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
□■フエンテ東久留米■□
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
田宮選手、地域を問わず移籍を重ねてますね!まだまだ活躍されるでしょう、期待です。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
CSLの2020シーズンレギュレーションにデッツォーラ島根の名前はありませんね。今シーズンは参加を見送りでしょうね、残念ですが。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
日本フットボールリーグは、日本のサッカーリーグである。公益財団法人日本サッカー協会と一般社団法人日本フットボールリーグが主催・運営する。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■Jリーグとの関係と位置づけ
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■歴史
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
この後、JFLに加盟する準加盟クラブのうち10クラブがJ3ライセンスを取得したことを受けて、JFLは2014年度の新規参加希望クラブを地域リーグ以下に属するクラブに対し募集し、北海道を除く全国8つの地域から25クラブ(内訳:北海道0、東北3、関東4、北信越3、東海4、関西5、中国4、四国1、九州1)が加盟申請を行った。今後は、J3加盟クラブの正式決定や第37回全国地域サッカーリーグ決勝大会の結果を踏まえて、12月4日をめどにJFL理事会で参加チームを正式に決定するとしている。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
J3発足後のJFLのあり方については、JFLに残留するクラブの担当者有志を中心に議論が行われている。「仕事と両立しながらサッカーをするのが最大の特徴。“アマ最高峰”をさらに強く打ち出すべき」との意見の一方で「プロを目指すクラブの行く手を阻もうと企業チームなどが奮起し、リーグが活性化してきたのも事実だ」との意見もあった。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
2003年・第5回
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
2010年・第12回
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
2015年・第17回
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■テゲバジャーロ宮崎 九州 / 宮崎県
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■過去に所属していたクラブ
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■Y.S.C.C.
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■流経大ドラゴンズ龍ケ崎
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■ファジアーノ岡山ネクスト 中国
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
2011年度までは後述の天皇杯出場枠の決定などの便宜上、1回戦総当り(17試合)を前期と後期に分けているが、順位自体は通年で決定しており、実質的に1シーズン制(2回戦総当たり)であった。2012年度も天皇杯出場決定は1回総当り終了時点(第17節)の順位で行うものの、節数の表示には「前期・後期」を用いなくなり、Jリーグと同じく1年間通しで表示(最終は第34節)となった。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■大学チームの参加
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■天皇杯のシード権
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
2014年以降、降格クラブが2クラブとなり、入れ替え戦は行われなくなった。JFL・地域リーグ間でのクラブの昇降格は、基本的に以下のルールで行なわれている。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
◇2012・2013年度
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
J3スタジアム要件に関する審査を受け、合格すること。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■キャッチフレーズ
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
 ポスト
ポスト