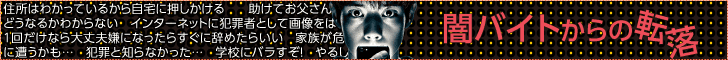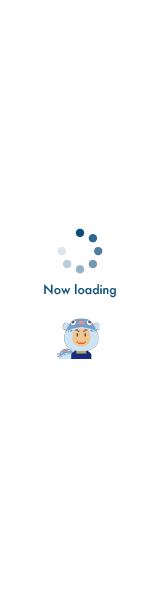さらに1990年代後半に入ると九州各県からJリーグ加入を目指す動きが起き始め、それに伴い強化を図るクラブチームが頭角を現した。このため1989年に優勝したのを最後に徐々に成績を落とし優勝から遠ざかっていった。
■ニューウェーブ北九州
2001年、地域密着型のサッカー・スポーツクラブの創設を目標として、北九州市と地元企業などが共同で特定非営利活動法人北九州フットボールクラブ(北九州FC)を創設し、当時九州リーグに所属していた三菱化学黒崎フットボールクラブの運営を北九州FCに移し、チーム名を「ニューウェーブ北九州」に改め、北九州FCのトップチームになった。元々ニューウェーブ北九州という名前は、北九州市長杯争奪北九州招待サッカー大会に出場するため三菱化成黒崎サッカー部と新日鐵八幡サッカー部から選出された北九州市選抜チームに対して付けられていた名前であった。
クラブは「北九州からJリーグチームを」というスローガンを掲げ当初からトップチームのJリーグ参加を目指し、地元資本である井筒屋やゼンリンなどのスポンサードを受けたり、北九州市内に設置されているコカ・コーラの自動販売機の売上の一部が運営費に贈られた。
2005年、サガン鳥栖元監督で北九州市出身の千疋美徳が監督に就任。リーグ戦は6位の成績。
2006年、千疋が監督を続投し、従来からのスポンサーに加え北九州市からの支援も受けた。リーグ戦は3位、全国社会人サッカー選手権大会は準決勝で静岡FCに敗れた。福岡県サッカー選手権大会(兼第86回天皇杯全日本サッカー選手権大会福岡県予選)は東海大五高校に敗れた。
■ニューウェーブ北九州
2001年、地域密着型のサッカー・スポーツクラブの創設を目標として、北九州市と地元企業などが共同で特定非営利活動法人北九州フットボールクラブ(北九州FC)を創設し、当時九州リーグに所属していた三菱化学黒崎フットボールクラブの運営を北九州FCに移し、チーム名を「ニューウェーブ北九州」に改め、北九州FCのトップチームになった。元々ニューウェーブ北九州という名前は、北九州市長杯争奪北九州招待サッカー大会に出場するため三菱化成黒崎サッカー部と新日鐵八幡サッカー部から選出された北九州市選抜チームに対して付けられていた名前であった。
クラブは「北九州からJリーグチームを」というスローガンを掲げ当初からトップチームのJリーグ参加を目指し、地元資本である井筒屋やゼンリンなどのスポンサードを受けたり、北九州市内に設置されているコカ・コーラの自動販売機の売上の一部が運営費に贈られた。
2005年、サガン鳥栖元監督で北九州市出身の千疋美徳が監督に就任。リーグ戦は6位の成績。
2006年、千疋が監督を続投し、従来からのスポンサーに加え北九州市からの支援も受けた。リーグ戦は3位、全国社会人サッカー選手権大会は準決勝で静岡FCに敗れた。福岡県サッカー選手権大会(兼第86回天皇杯全日本サッカー選手権大会福岡県予選)は東海大五高校に敗れた。
 ポスト
ポスト