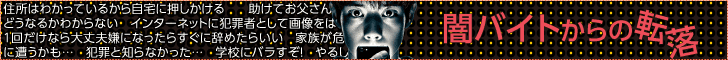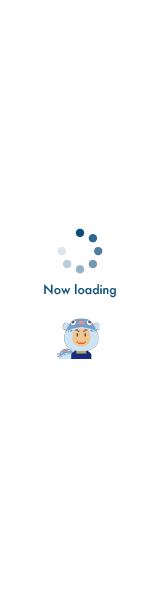杉山 隆一は、静岡県清水市 (現:静岡市) 出身の元サッカー選手、サッカー指導者。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■来歴
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■エピソード
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
ヤマハ発動機サッカー部は、かつて存在した日本のサッカークラブ。ヤマハ発動機のサッカー部として1972年に創部。呼称はヤマハ。日本プロサッカーリーグに加盟するジュビロ磐田の前身となったクラブであり、ジュビロと同じく静岡県磐田市を中心に活動していた。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
その後はタイトル獲得は成らなかったものの、読売クラブや日産自動車に継ぐ3番手のクラブとして1980年代中盤から1990年代初頭のJSLを盛り上げる存在であった。 また隣接する浜松市を本拠地とした本田技研とはライバル関係にあり、その一戦は「天竜川ダービー」、「天竜川決戦」と呼ばれリーグ屈指の好カードとなった。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■略歴
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
「Category:ヤマハ発動機サッカー部の選手」も参照
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
渡邉 恒雄(わたなべ つねお、1926年〈大正15年〉5月30日 -)は、日本の新聞記者、実業家。株式会社読売新聞グループ本社代表取締役主筆。勲等は旭日大綬章。「ナベツネ」の通称で知られる。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
その後、地域に根差したクラブの運営により裾野からのサッカー人気向上を図るJリーグや日本サッカー協会と、「読売ヴェルディ」の巨人化を目論む読売グループ間の対立が表面化した。グループ放送局のテレビ中継で使用していた「読売ヴェルディ」の呼称を「ヴェルディ川崎」に改めるようJリーグ執行部から指摘を受け、1994年からJリーグの勧告を受け入れ、「読売」を外して「ヴェルディ川崎」とアナウンス・表記されるようになった。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
ファンにしてみたらこれらの無関係な長文の連投は本当に迷惑だよ。これ以上続けるならバクサイ運営に利用規約違反として通報するからね。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
読売サッカークラブは、かつて存在した日本のサッカークラブ。読売新聞社、株式会社よみうりランドが主体となって1969年に創設された。呼称は「読売」もしくは「読売クラブ」。日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)に加盟する東京ヴェルディ1969の前身となったクラブである。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
1968年秋に全日本大学サッカー選手権大会で優勝した東京教育大学蹴球部(現:筑波大学蹴球部)監督の成田十次郎に野津から電話があり、「読売の正力さんが、いずれ野球の次はサッカーのプロ化の時代が来るといっている。君はヨーロッパのサッカーに通じているので、一つ協力してやってくれないか。読売新聞と日本テレビが協力して、読売ランドの中に芝生一面を含む四面のサッカー場とクラブハウスを設置して、ヨーロッパのようなクラブ組織を作る。それをプロへつなげるという仕事をして下さい」という説明があった。成田は野津の要請をただちに承諾、間もなく日本テレビの笹浪永光(笹浪昭平)が成田の自宅を訪れ、「経済的には、読売新聞社、日本テレビ、よみうりランドが支援し、折衝には私が責任を持つので監督に」という要請があり、笹浪から「できるだけ早く上のリーグへ昇格することと、クラブが募集する少年たちの指導のために、東京教育大学の選手を連れてきてもらいたい」との依頼を受け、当時監督を務めていた東京教育大学の選手を連れて成田が読売クラブの初代監督に就任した。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
クラブの実質的責任者は日本テレビの笹浪永光(笹浪昭平)で、チーム作りは監督の成田が行った。結成前に日本テレビ放送網の実業団サッカー部(日本テレビ・サッカー部)があり、東京教育大学全日本大学サッカー選手権優勝時の主将・柴田宗宏が1969年春、同大学を卒業しコーチとしてこのチームに加わり、東京都社会人サッカーリーグ2部(B)に加盟。正式に「読売サッカークラブ」と正式にチーム名を改めたのは1970年2月。柴田が首都圏の学校に就職していた仲間を加え、その後はとんとん拍子に昇格した。「読売サッカークラブ」は先の「日本テレビ・サッカー部」を発展解消させたとも言われる。ただ成田十次郎は「日本テレビ・サッカー部」のメンバーは1969年3月31日に卒業したと話している。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
当初は柴田宗宏を選手兼指導者として迎え、柴田、高田静夫、野地照樹ら東京教育大学出身者を選手強化の中核とすると共に、少年指導にも当らせた。「練習グランドを作り、少年達を育てる」ことに重点が置かれ、欧州型のサッカークラブに倣い下部組織からトップまで使用できる練習グラウンドをよみうりランド内に建設、東京ヴェルディとなった現在もここを練習場として使用している。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
この後、西邑昌一監督、相川亮一コーチに移行し、1977年にジャイロ・マトスらを迎え4度目の挑戦で初のJSL1部昇格を果たした。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
かつては「アウトロー」とも評されたクラブも、1986年の武田修宏、1990年の三浦知良、1991年の北澤豪らの加入により都会的なイメージの集団へと変化していった。そのイメージはJリーグ開幕以降もしばらく引き継がれていった。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■読売クラブ出身の主な選手
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■下部組織
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
日産自動車サッカー部は、かつて存在した日本のサッカークラブ。日産自動車のサッカー部として1972年に創部した。呼称は「日産」。日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)所属の横浜F・マリノスの前身となったクラブである。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
しかし、1部昇格初年度となる1979年シーズン、1部最下位の10位に終わる。同年は最下位も2部1位との入替戦により昇降格を決定する方式であったため、2部優勝の東芝堀川町サッカー部(現:北海道コンサドーレ札幌)と対戦、連勝し1年での2部降格は免れたが、翌1980年シーズンも2年連続で最下位となり、この年は最下位が2部強制降格となるレギュレーションであったため、3シーズンぶりの2部所属となった。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
1987年に元ブラジル代表の主将ジョゼ・オスカー・ベルナルディを獲得。オスカーの加入は守備面の修正とプロ意識をもたらし、1988-89シーズンではJSL、天皇杯、JSLカップの三冠を達成。その後も、JSL末期の1980年代後半から1990年代初頭に数多くのタイトルを獲得した。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■日産自動車出身の主な選手
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■Category:日産自動車サッカー部の選手も参照
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■横浜F・マリノスと異なる点
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
トヨタ自動車工業サッカー部は、かつて存在した日本のサッカーチーム。トヨタ自動車工業のサッカー部として1939年に創部され、1983年にトヨタ自動車工業がトヨタ自動車販売と合併しトヨタ自動車が誕生した事に伴い「トヨタ自動車サッカー部」に改称された。呼称はトヨタ。日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)に加盟する名古屋グランパスエイトの母体となったクラブである。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
そこで東京本社の総務部長で愛知県サッカー協会技術委員長であった西垣成美が奔走し、この決定を覆す事に成功した。これには県サッカー協会による署名活動や地元メディアと連携し運動を盛り上げた事も後押しとなった。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■エピソード
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
東洋工業サッカー部は、かつて存在した日本のサッカークラブ。日本プロサッカーリーグに加盟するサンフレッチェ広島の前身となったクラブである。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■略歴
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■ユニフォームカラー
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
戦後復興の最中、蹴球部も1947年(昭和22年)に再開する。以降銭村健次・小畑実ら地元出身の有力選手の入団が相次ぎ、当時の主要タイトルである全日本選手権(天皇杯の前身)・全日本実業団・国体に常に優勝争いを繰り広げる実業団の強豪チームを作り上げた。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
1955年(昭和30年)、全日本実業団でまたも準優勝(0-2対田辺製薬)。1956年(昭和31年)、田辺製薬の7連覇を阻みついに全日本実業団で優勝して初の全国タイトルを獲得した(4-0)。1957年(昭和32年)も第37回天皇杯で決勝進出、広島国泰寺高校で決勝戦が行われたが準優勝(1-2対中大クラブ)に終わる。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
この1965年から1970年がこのクラブの黄金期である。JSL第1回大会を12勝2分け0敗と無敗で優勝。第1回大会第14節・対ヤンマー戦(現:セレッソ大阪)で記録した11-0(桑田:5・小城:4・松本:2)は、最多得点及び最多得失点差11点のJSL最高記録。第2回大会まで23連勝を記録するなど、第4回大会まで不滅のリーグ4連覇の金字塔を樹立し第6回大会も制覇したことによりJSL27回の歴史で最多の5回の優勝を飾った。更に天皇杯では第45回大会で初優勝すると、6年で決勝に5度進出し3度の優勝を飾った。また国際舞台では、アジアクラブ選手権1969に日本勢として初出場し3位入賞を果たした。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
◇1970年代
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
◇1980年代
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
1988年(昭和63年)、今西はビル・フォルケスをコーチとして招聘し、オフトの役割だった実質的な監督として置いた。フォルケスは母国の戦術で古い戦術でもあるキック・アンド・ラッシュ戦術を用いたが、オフト時代のアプローチと変わったこともあり一部選手には不評だった。1989年(平成元年)、当時2. ブンデスリーガでプレーしていた元日本代表の風間八宏を獲得する。マツダSC東洋で育成した選手達の成長もあって1991年(平成3年)にJSL1部復帰。日本リーグ最後の年となった1991-92シーズン、フジタ(現:湘南ベルマーレ)から移籍加入した高木琢也の活躍もあり、6位で面目を保った。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
2013年現在Jリーグ最高齢監督記録保持者である松本育夫は元東洋工業監督である。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■歴代監督
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■歴代選手
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■参考資料
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
三菱重工業サッカー部は、かつて存在した日本のサッカークラブ。中日本重工業のサッカー部として創部した。呼称は三菱。Jリーグに加盟する浦和レッズの前身となったクラブである。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
1958年、新三菱重工が本社を東京に移転したため、サッカー部選手の大半も東京に転勤して、三菱は東京のチームとなる。1964年、3社の再統合により社名が「三菱重工業」に変わり、チームも「三菱重工業サッカー部」となった。日本サッカーリーグ(JSL)では、1965年の創設時から参加しており、JSL通算最多勝利・通算最多勝ち点を記録する。また、古河(現ジェフユナイテッド市原・千葉)、日立(現柏レイソル)と並んで、丸の内御三家の一角を成し、リーグ運営の中心にあった。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
1975年には三菱グループ創業100周年の記念事業の一環として東京都豊島区巣鴨に総合スポーツクラブ「三菱養和クラブ」が設立されたが、森健兒はこの事業に尽力している。また、同クラブのサッカースクールには三菱サッカー部OBが指導者として迎えられ、ユース年代の各大会で好成績を収めると共に多くの選手を輩出した。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
Jリーグ創設前の通算成績は、JSL優勝4回、天皇杯優勝4回。JSLは全27シーズン中26シーズンを1部で過ごし、その通算成績は460戦211勝117分け132敗、総得点682、総失点507。JSL1部を経験した全22チーム中最高の数字だった。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■略歴
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■三菱重工業サッカー部に所属した主な選手
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■「Category:三菱重工業サッカー部の選手」も参照
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
■三菱重工と浦和レッズで異なる点
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
本田技研工業株式会社フットボールクラブは、日本の浜松市北区を本拠地とする日本フットボールリーグ(JFL)に所属する社会人サッカークラブ(実業団)。呼称は「Honda FC」(ホンダ エフシー)であり、以下の文章からは基本的に呼称で表記していく。
[匿名さん]
?
Good!
?
Bad
 ポスト
ポスト